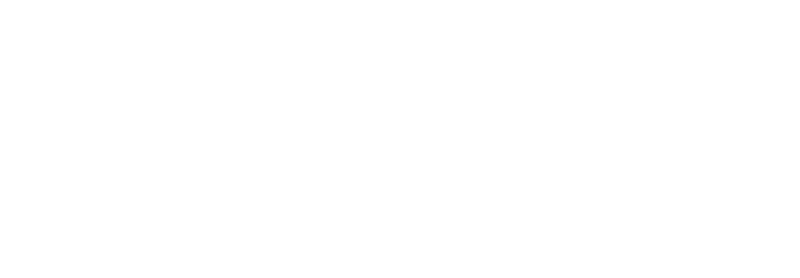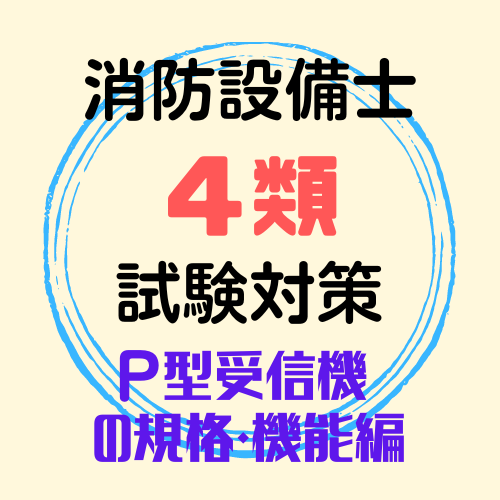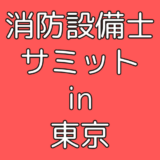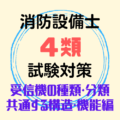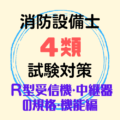皆さんこんにちわ。
前回の受信機の種類・分類と共通の構造・規格編に続きまして今回はP型受信機について
- P型受信機の種類と規格・機能
これらについて解説していきますが今回も重要な所や覚えたい所は やアンダーラインを引いていますので参考にしてください。
やアンダーラインを引いていますので参考にしてください。
P型受信機の定義

P型1級受信機(多回線)の例
 P型受信機とは上の写真の様な受信機で、以前の記事でも解説したように1級~3級に分かれており、かつ回線数(多回線・1回線)も関係しています。
P型受信機とは上の写真の様な受信機で、以前の記事でも解説したように1級~3級に分かれており、かつ回線数(多回線・1回線)も関係しています。
ちなみにP型受信機の定義は
火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
となっています。
P型受信機を機能や回線数で分けると
- P型1級(多回線)
- P型1級(1回線)
- P型2級(多回線)
- P型2級(1回線)
- P型3級(1回線)
となっており、設置しようとする防火対象物の規模に応じて機器を選定します。
このP型受信機で覚えておきたい所は全ての機能を備えた「P型1級(多回線)」の構造・機能で、それ以外のP型受信機はこのP型1級(多回線)の機能を一部免除されているので、どの受信機は何の機能が設置されているのかを整理して覚えておくとスムーズだと思います。
P型1級受信機(多回線)

P型1級(多回線)受信機の例
 このタイプの受信機は回線数に制限がないので、中~大規模の防火対象物に良く設置されています。
このタイプの受信機は回線数に制限がないので、中~大規模の防火対象物に良く設置されています。
この「回線数に制限がない」は重要なので良く覚えておきましょう。
P型1級受信機の主とする機能
 P型1級受信機(多回線)が持っている機能を解説していきますが、受信機が感知器や発信機から火災信号を受信した場合の動作としては
P型1級受信機(多回線)が持っている機能を解説していきますが、受信機が感知器や発信機から火災信号を受信した場合の動作としては
- 赤色の火災灯が点灯する
- 火災信号を送出した警戒区域の地区表示灯が点灯する
- 主音響装置が鳴動する
- 地区音響装置が鳴動する
これらの動作を行い受信機周辺の関係者及び在館者へ火災発生を知らせる機能を持っています。
- 地区表示灯
- 感知器や発信機から火災信号を受信した(発報した)警戒区域を表示する部分で防火対象物の階層や部屋などが記載されている(1階や2階、事務室や階段など)
- 火災灯
- 感知器や発信機から火災信号を受信した時に点灯する赤色の表示灯
- 主音響装置
- 受信機本体に内蔵されている音響装置で、受信機周辺にいる関係者へ火災発生を知らせるもの、1m離れた位置で85dB以上(A特性)の音圧が必要
- 電話ジャック(通話装置)
- 発信機に専用の送受話器を差し込むと受信機の「電話灯」が点灯しブザー(又は呼び出し音)が鳴り発信機に送受話器が差さっていますよと教えてくれるので、受信機の電話ジャックにも専用の送受話器を差し込むと受信機と発信機の間で通話ができる装置
- 火災試験(火災表示試験装置)スイッチ
- 火災表示の作動試験を行う為の装置で「回路選択スイッチ」で火災表示試験を行いたい警戒区域を選択して火災表示試験を行う
- 電池試験(予備電源試験)スイッチ
- ブレーカーなどを操作しなくても受信機の盤面で電源切替試験を行える装置で、試験を行うと予備電源に切り替わり、試験を止めると主電源に自動的に切り替わる、跳ね返り式のスイッチで操作しても手を離すと元に戻る
- 消火栓連動スイッチ
- 消火栓連動遮断スイッチとも言い、発信機の作動試験を行う際に消火栓ポンプが起動しないように起動信号の送出を遮断できるスイッチ
- 受信機によっては受信機から遠隔で消火栓ポンプを起動することができる「消火栓起動スイッチ」が設置されているものもある(消火栓ポンプの停止は消火栓ポンプの制御盤の停止スイッチを押さなければならない)
- 消火栓連動遮断スイッチの他にも防火戸や防火シャッター等への作動信号の送出を遮断する「連動遮断スイッチ」や、警備会社や非常放送設備等への信号を遮断する「移報遮断スイッチ」もある
- 地区音響装置
- 受信機の火災表示と連動して館内の地区音響装置(ベルやサイレンなど)を鳴動させるもので、1m離れた位置で90dB以上(A特性)の音圧が必要(音声を発するものはA特性で92dB以上)
- 交流電源灯
- 交流電源(主電源)が接続されていろ事を表す緑色のランプ、停電するとランプが消える
- 電圧計
- 受信機内部の回路電圧を示してくれる、基準電圧は直流24Vで予備電源試験をした際の電圧も示してくれる
- 発信機灯
- 受信機側で発信機が押されている事がわかるランプで、感知器が作動いたのか発信機が作動したのかを区別できるようになっている
- 火災表示の自己保持
- 感知器や発信機からの火災信号をうけて受信機が火災表示を行っている時は、感知器や発信機が復旧(正常状態に回復すること)しても受信機は火災表示をずっと行います、これを「火災表示の自己保持」といい「復旧スイッチ」を操作して手動で火災表示を復旧しない限り火災表示をし続ける機能
- 試験復旧スイッチ
- 感知器の点検などで感知器を作動させると上記の様に自己保持してしまい感知器作動の度に復旧スイッチを操作しなければならないが、この試験復旧スイッチをONしておけば自己保持機能を解除して感知器が復旧すると同時に受信機の火災表示も一緒に復旧してくれる機能で主に点検時に使用するスイッチ
- 復旧スイッチ
- 自己保持されている火災表示を手動で復旧させる為のスイッチでいわゆるリセットスイッチ、跳ね返り式のスイッチで操作しても手を離すと元に戻る
- 導通試験スイッチ
- 各警戒区域の回路(感知器を繋いでいる配線)に断線が無いかを確認できる機能、自動的に断線を監視・検出できる機能があればこのスイッチを設けなくても良いので最近の受信機は自動断線検出機能を搭載して導通試験スイッチを設けていない受信機が多い
P型1級受信機(1回線)
 この受信機は回線数が1しかないので、警戒区域が1つしかない場合にしか設置することができない受信機になり、以下の機能を持っています
この受信機は回線数が1しかないので、警戒区域が1つしかない場合にしか設置することができない受信機になり、以下の機能を持っています
- 火災表示の自己保持
- 火災表示試験
- 予備電源
- 主音響装置(A特性で85dB以上)
- 地区音響装置(A特性で90dB以上)(音声を発するものはA特性で92dB以上)
P型2級受信機(多回線)

P型2級受信機(多回線)の例
 このP型2級受信機(多回線)は回線数に制限があり、最大で回線数は5回線までと決められているので小規模な防火対象物向けの受信機となっていて、機能は以下の通りです。
このP型2級受信機(多回線)は回線数に制限があり、最大で回線数は5回線までと決められているので小規模な防火対象物向けの受信機となっていて、機能は以下の通りです。
- 地区表示灯
- 予備電源
- 火災表示試験
- 火災表示の自己保持
- 主音響装置(A特性で85dB以上)
- 地区音響装置(A特性で90dB以上)(音声を発するものはA特性で92dB以上)
P型2級受信機(1回線)とP型3級受信機
 この2つの受信機はそんなに相違点が無いのでまとめて解説しますが、両方とも回線数は1回線なので警戒区域も1つしか設定できません。
この2つの受信機はそんなに相違点が無いのでまとめて解説しますが、両方とも回線数は1回線なので警戒区域も1つしか設定できません。
機能は以下のものがあります
| P型2級受信機(1回線) | P型3級受信機 |
| 火災表示試験 | 火災表示試験 |
| 主音響装置(A特性で85dB以上) | 主音響装置(A特性で70dB以上) |
| 火災表示の自己保持 |
上記の表からも解るようにP型3級受信機は主音響装置の音圧が70dB以上で良いことと、火災表示の自己保持機能が無いのでそれに伴い「復旧スイッチ」もありません。(感知器が復旧すれば受信機の火災表示も復旧する為)
P型受信機の機能まとめ
 上記で解説した機能の一覧は以下の表のとおりになります(〇印は必要の意味)。
上記で解説した機能の一覧は以下の表のとおりになります(〇印は必要の意味)。
| P型1級 (多回線) |
P型1級 (1回線) |
P型2級 (多回線) |
P型2級 (1回線) |
P型3級 (1回線) |
|
| 火災灯 | 〇 | ||||
| 発信機灯 | 〇 | ||||
| 通話装置 | 〇 | ||||
| 導通試験 | 〇 | ||||
| 地区表示灯 | 〇 | 〇 | |||
| 予備電源 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 火災表示の自己保持 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 火災表示試験 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主音響装置※1 | 85dB以上 | 85dB以上 | 85dB以上 | 85dB以上 | 70dB以上 |
| 地区音響装置※1※2 | 90dB以上 | 90dB以上 | 90dB以上 |
※1…音圧は全てA特性
※2…音声を発する地区音響装置の場合は92dB以上
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回はP型受信機について各受信機に備わっている機能とその解説について説明させていただきましたが、毎度同じで重要な部分にはアンダーラインや 重要度にてお知らせしていますので良く覚えておきましょう。
重要度にてお知らせしていますので良く覚えておきましょう。
今回の重要部分のなかでも特に覚えていただきたいのが
- P型1級受信機の主とする機能
- 各受信機に接続できる回線数
- 予備電源の設置の要不要
- 各音響装置の音圧(70、85、90、92dB)
これらは覚えておいて良いと思いますし、あとは1回線の各受信機でどの機能が搭載されているかも振り分けができるとなお良いと思います。